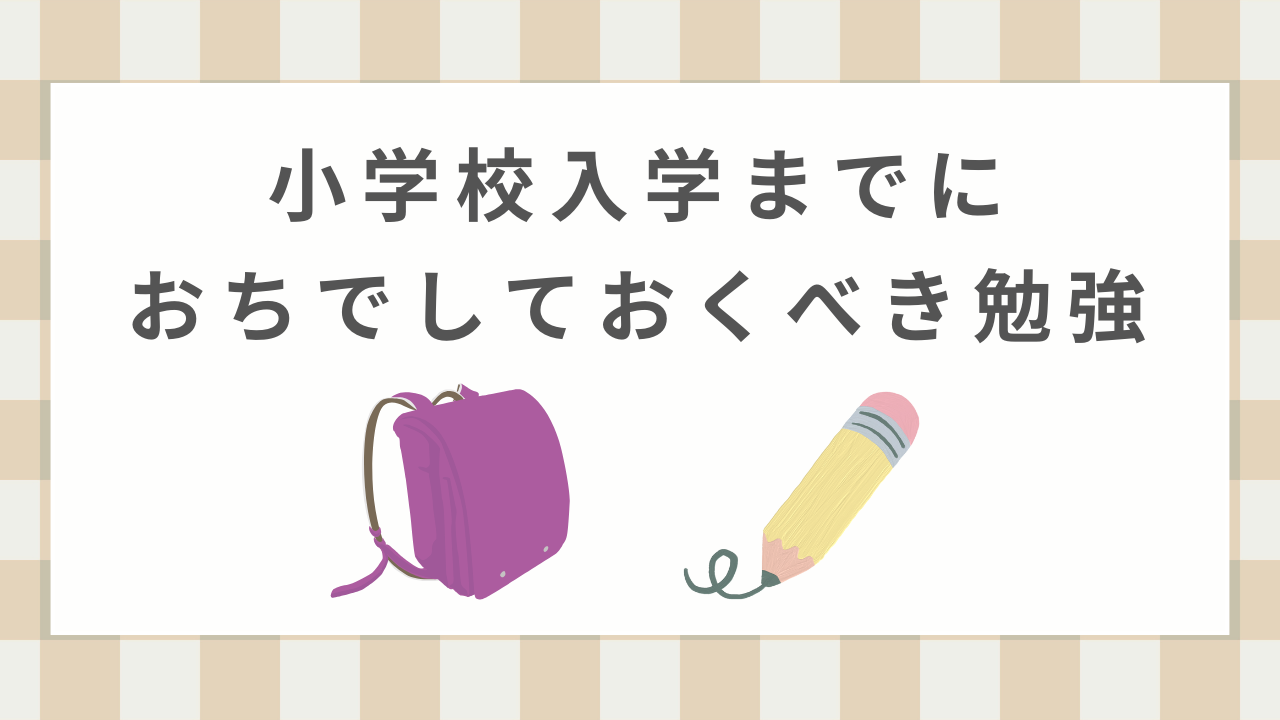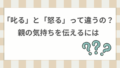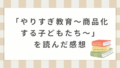こんにちは。さんははです。
今回は、
小学校入学前の勉強「ひらがな・カタカナ・簡単な足し算・時計」のお勉強の準備についてご紹介します。
初めてのお子さんが小学校に入学する前は、親も期待と不安で、ドキドキしますよね。
小学校では、通常10月~11月ごろに入学前検診があるようです。
その時に、入学までに、「自分の名前を読めて、書けるようにだけしておいてください。」と言われます。

でも、本当にそれだけでいいのでしょうか・・・?
私はそれだけでは、正直不足だと思います。
小学校生活に、スムーズに慣れて楽しく通うためにも、
「ひらがな・カタカナ・簡単な足し算・時計」はできるようにしてから送り出してあげることが必要だと思います。
その方が、本人も心に余裕をもって授業に取り組めるからです。
また、実際に子どもだちの様子を見ていて、
小学校の勉強と宿題だけではどうしても量が少ないので、身に付きにくいというのが現実だと感じています。
宿題だけでは、必要な量がこなせない
↓
結果、きちんと身につかない
ということになってしまいがちです。
だから、1年生の最初のスタートが肝心ですので、入学前のお勉強はぜったいにおすすめ!
でも、
そもそも、「ひらがな・カタカナ・簡単な足し算・時計」、いつから、どうやって教えるのがいいの・・・?
と思いますよね。
そのために習い事に通わせるのも大変です。
なので、今回は
自宅でできる、入学前の勉強方法についてご紹介します。
みなさんのお子さんがスムーズに小学校生活に慣れていけるよう、参考になると幸いです。
いつから勉強を始めたらいいの?
1~2歳ごろから知育おもちゃで遊びながら学ぶ
できれば、1~2歳ごろから、知育おもちゃで遊びながら、自然にひらがなや数字に触れられるようにしてあげることをおすすめします。
おもちゃを選ぶ時には、「勉強になるかな?」という視点でも選んであげてください。
でも、たくさん種類がありすぎて迷いますよね。私はこんな視点で選んできました。
・時計や時間にも自然に興味をもてるようなもの
・子どもが好きなキャラクターを選ぶ
・目が悪くならないもの(※知育パッド等は選びませんでした)
2~3歳ごろから はじめての文房具 はじめてのドリル(くもん)
そして、2~3歳ごろになると、鉛筆を持てるようになりますので、最初は運筆のドリルからはじめてください。「運筆」や「めいろ」のドリルです。
最初は、くもん文房具がおすすめ!
なお、まだ筆圧が弱いので、幼児用の「こどもえんぴつ」も用意してあげてください。
わたしは、くもんの「こどもえんぴつシリーズ」を一式そろえて使っていました。
くもんの「こどもえんぴつ」は、太くて、さんかくえんぴつ、筆圧が弱くても書きやすいように工夫されています。
はじめは、B6から始めてください。一番柔らかくて、短いので、小さい子どもでも本当に持ちやすいです。
持ちやすく、書きやすいので子どもも書けることに喜びます。本屋さんのくもんドリルコーナーにも置いてあります!
そろえたらいいものまとめ ↓
・くもんのこどもえんぴつもちかたサポーター 308円(税込)
・くもんのこどもえんぴつけずり 308円(税込)
※この専用のえんぴつ削りが必要です。こどもえんぴつの太さと、通常の太さのえんぴつ、両方が削れるようになっています。とても削りやすいので、幼児期以降も使えるので、おすすめです。
・くもんのこどもいろえんぴつ 638円(税込)
※なくても進められますが、小さな手でも握りやすく書きやすいのでおすすめです。ドリルをするときに色を変えて楽しめます。
全部そろえても、合計1749円(税込)です。
※2023年11月での情報です。くもん出版公式ページより
なんと、検索していたら、くもんこどもえんぴつセットもあるようです。↓(実店舗ではみたことないのですが・・・)
濃いえんぴつ用消しゴム(トンボ製品)とキャップ(くもん)がついていますが、※色鉛筆はついてません。
はじめてのドリル(くもん)
はじめてのドリルも、くもんのドリルがおすすめです。
くもんの幼児ドリルシリーズは、色がやさしくて、絵もかわいいし、大きくて見やすいので、いろいろ他もみましたが、やっぱりくもんのドリルが一番いいな~と思いました。
最初はうまく書けないと思いますが、それでOKです。少しづつ、だんだん上手にできるようになっていくと思います。
つぎはめいろのドリル(くもん)
「はじめてのおけいこ」ができたら、次はいきなりひらがなではく、めいろのドリルがおすすめです。
遊びの延長で取り組めるので、子どもも無理なく進められます。
めいろで運筆に慣れてから、ひらがなのドリルに進むのがスムーズだと思います。
ひらがなを覚えよう(3歳ごろ)
めいろがなんとなく上手にできるようになってきたら、ひらがなのドリルに進んでOKだと思います。
3歳~年少さんの年頃になってきたら、はじめ時です。
本人も文字に興味をもっていると思いますので、ゆっくりでいいので、すすめていってください。
なお、入園されている子ども園によっては、ひらがなやカタカナ、数字、簡単な足し算まで教えてくれる園もあれば、全く教えてくれない園もあるようです。
教えてくれると思っていたら、全然教えてくれていなかったと焦らないためにも、
一度、子ども園の先生に園での勉強の取り組みについて、お聞きされることをおすすめします。
家でどのように教えたらいいかもアドバイスしてくださるかもしれません。
ちなみに、入園する際に勉強の有無を確認してから園を決めることも大切です。
やはり家で教えるより、集団生活の中で習う方が、子ども自身もやる気になり、身に付きやすいと感じます。
えんぴつの持ち方をみてあげる
子ども園の進度に合わせて、家でもドリルに並行して取り組み、
必ずえんぴつの持ち方や、書き順なども見てあげてください。
年齢があがるにつれ、治りにくくなります。
まだ言うことを聞いてくれるうちに、えんぴつの持ち方を見てあげてください。
本当に、「鉄は熱いうちに打て」です。その時その時に伝えないといけないことがあるんです。
はじめてのひらがなのドリル
ひらがなも、くもんのドリルがおすすめです。
最初は「はじめてのひらがな①」から始めて、順番に次のドリルに進めていってください。
まだできていないと感じたときは、同じドリルを何回も繰り返すのも効果的です。できれば、3歳~5歳くらいの間に順番にゆっくり進めていくのがいいと思います。だんだんひらがなが読めるようになってくると本人も喜びます。そして文字を書きたがるようになります。
数字を覚えよう(4歳ごろ)
数字も1~10は必須で、読めて、書けるようにしておいてください。4歳くらいで分かってきます。また、100までは数えられるように、お風呂で100まで数えるのも大事です!
おすすめはくもんのドリルです。まずは、この1冊だけで十分です。
カタカナを覚えよう(5歳ごろ)
ひらがなが読めて、書けるようになってきたら、その次に、できればカタカナも覚えておいた方がいいと思います。カタカナは5歳ごろ(年長)に始めるのがちょうどいいです。
完璧に覚えなくていいので、「なんとなく分かっている」「読めて、書ける方カタカナもある」という感じでOKです。それだけで子どもは少し自信をもって望めます。「シ」「ツ」の区別など、小学生で習う段階でも、ややこしいと感じるようですので、入学前の段階で完璧にする必要はないと思います。小学校で習い、他のお友達にと一緒に、だんだんと覚えますので大丈夫です。
時計をよめるようになろう(5歳ごろ)
時計も「なんとなく読める」ようになっていた方がいいと思います。
細かい何時何分までは読めなくてもOKですが、
1時、2時、3時・・・と針が進んでいくことや、大まかな時間(何時半)は分かるようにしてあげた方がいいです。
時計は、まずは、時計の絵本や、時計のおもちゃで遊んで時間の概念をなんとなく分かっていくことと、小さいころから、「今3時だね。短い針が3で、長い針が一番上にきているね。」などと声かけをしていくのも大事だと思います。
また、子どもが「今何時?」とよく聞いてくる時期がありますので、その時が時計に興味をもったということですので、そのタイミングで教えていってあげるのがいいかなと思います。うちの子は、4歳ごろが、「いま何時?」とよく聞いてくる時期でした。そのタイミングでダイソーの時計のおもちゃを欲しがったので買いました~。
ドリルもできればこの1冊だけはしておいた方がいいかもしれません。この1冊だけ入学直前でOKだと思います。
かんたんな足し算・引き算をできるようにしよう(5歳ごろ)
かんたんな足し算、引き算もなんとなく分かるようにしておいた方がいいと思います。
足し算は、はじめは、指をつかって、1 と 1 を合わせると何かな?という感じで遊び感覚で始めましょう。
1+1、1+2、1+3、、、、と進めていって、なんとなく足し算が分かるようにしてあげてください。
引き算も指を使って、2 から 1 をとると 何かな? というように進めていってください。
遊びの延長で興味を持つよう、お風呂に入りながらとか、お菓子を分けるときやみかんを数えながら、足し算・引き算の概念を伝えていくのがいいと思います。できなくても怒らないでくださいね。
繰り返しているうちに、そのうち分かるようになります・・・大丈夫!
その下地があってから、ドリルに取り組むのがいいと思います。
足し算がある程度進んでから、引き算に進むのがいいと思いますが、無理のないようすすめてください。だんだん難しくなるので、全部のシリーズをする必要もないと思います。
小学校で習うための予習ですから・・・できるところまででOK!
本人が望むのなら進めてもOKですが、無理に進めないように気を付けてください。
今すぐにできなくても、小学校で習って、必ずできるようになります。何もせずに入学するより、1冊取り組んだだけでも、安心です。
入学直前まで何も勉強していなかったら
もし、入学直前までに何も勉強してこなかった場合ですが、
入学前の春休みに取り組んでください。
少しでも、予習しているかどうかで違います!
そして小学校が始まったら、宿題は必ず目を通して、理解しているか見てあげてください。
また、宿題に加えて、くもんのドリルに取り組むことをおすすめします。
学校の宿題だけだと、どうしても量が少なく、身につかないと実感しています。
1年生から、学校で習う + 宿題 + くもんのドリル をすることが大切です。
まとめ
最後に、小学校に入学前の勉強について、まとめます。
ひらがな・数字は、読み書きができるように。
カタカナ・時計はだいたい分かるように。
足し算・引き算はできるところまで予習しておく。
はじめての文房具とドリルは「くもんシリーズ」がおすすめ。
こんな感じですすめていけば、勉強面では無理なく小学校生活が始められると思います。
みなさんのお子さんが、楽しい小学校生活を始められることを願っています。