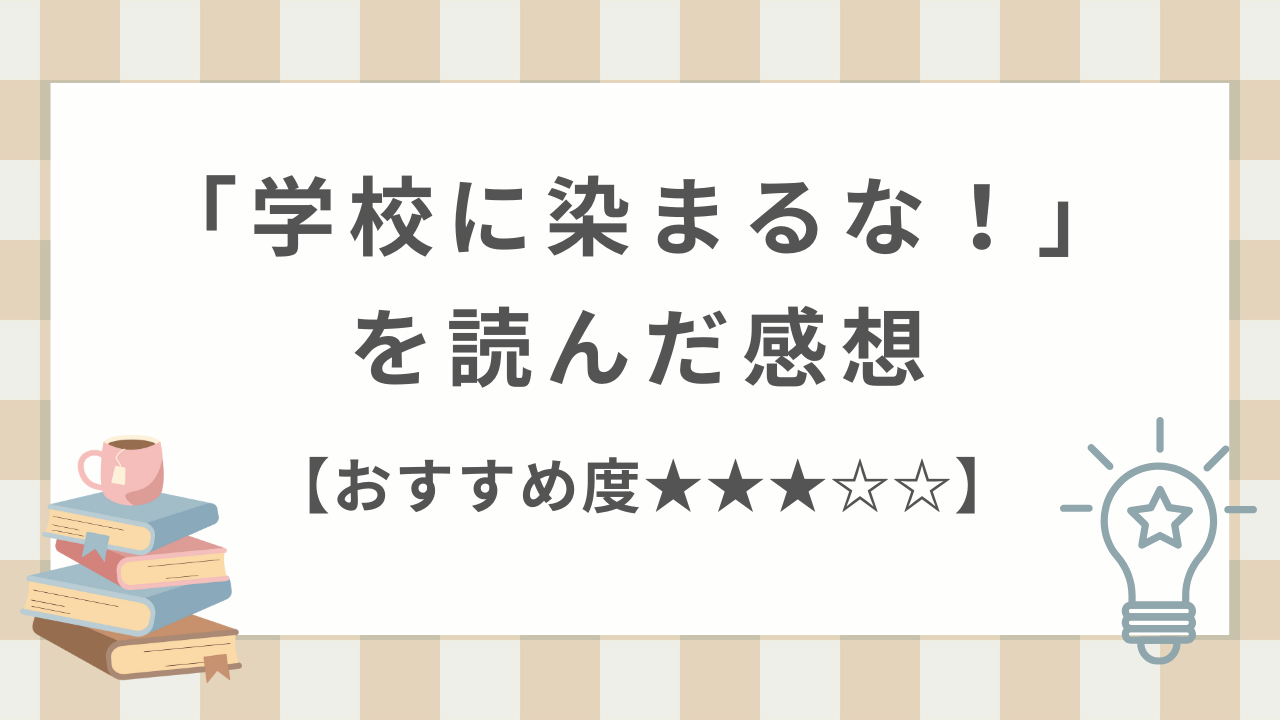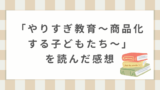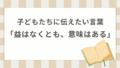おおたとしまさ氏の著書「学校に染まるな!」を読んだ感想と気づきをお伝えします。
おおたとしまさ氏は中学受験や教育に関する著書を多数出版されていますが、この本は、中高生向けに書かれた本です。
中高生が読んでくれたらいいのですが、少し堅い内容でしたので、まずは親目線で読ませてもらいました。
親や教育関係者の方が読まれても参考になると思います。
おおた氏が著述されているように今の教育状況には様々は課題はあると思います。
だからといってすぐに何かを変えられるわけでもありません。
だけど、子どもの学校、教育、進路、について親として考えるきっかけになると思いますので、簡単にご紹介します。
本の紹介「学校に染まるな!」(おおたとしまさ著)
著書は教育ジャーナリストのおおたとしまさ氏で、中学受験や教育関係の著書を多数出版されています。

まずは
楽天ブックスの内容紹介文から・・・
学校には、人類の叡智や希望が詰まっている。でも巧妙な出来レースも仕組まれている。さまざまな教育現場を見てきたプロが教える、学校をサバイブする方法。
「学校に染まるな!」(おおたとしまさ著)内容紹介(出版社より)引用

ちょっと気になりますよね
印象に残った内容を5つピックアップします
(1)正解を求めずにはいられない大人たち
世の中には正解があって、最短距離を進むべきだと教え込まれた大人たちは正解のない時代にも正解を求めてしまっている。そういう大人たちは予測できない未来に得をするための何かを子どもに授けようとして、本気でその何かを見出そうとしている。ギャグようだと皮肉を込めて述べられています。
(2)人材育成と教育は似て非なるもの
人材育成は社会で率先力となる人材を育てるよう、最短距離をいくことが正義になる。(置き換え可能な人間)かたや教育は回り道をしたり、立ち止まったりしながら、その人ならではの力を伸ばしていくこと。(置き換え不可能な人間)「人材育成」と「教育」をごっちゃにして語るなと述べられています。
(3)新しいものがいいとは限らない
新しいものがいいものだというのは現代にありがちな錯覚で、古くからあるものの価値もわかる人でいてほしい。今の世の中は、自分たちが運転する車のアクセルを踏み込みすぎていて、みんながレーシングドライバーの運転スキルを求めている。根本的に何かが間違っていると述べられています。
(4)家庭や学校の影響は意外と小さい
教育格差ができる構造として、遺伝的要因が無視できない。行動遺伝学者の安藤寿康さんによれば、学業成績の要因は、遺伝が50%、家庭環境が30%、その他が20%で、学業成績だけでなく、個人の得手・不得手のかなりの部分が遺伝で説明できるとのこと。もともと遺伝的要因が無視できないのに、勉強に関しては無理してでもさせるということが正義である気がしてしまうのが不思議だと述べられています。
(5)「足し算」よりも「引き算」
今は、マナーや道徳、コミュニケーション、キャリア教育、金融教育などあらゆることを学校に押し付ける社会。その末路が教員の長時間労働、その結果として教員不足、子どもにとっては学校での長すぎる拘束時間と放課後の消滅、ぼーっとする時間の消滅になった。この状況を変えるには、学校が抱え込んだ機能を日常生活や地域社会の中にもういちど戻す「引き算」をしなければならないと述べられています。
やっぱり遺伝とか、持って生まれた才能というのは、無視できないということは感じていましたが、さらに確信を持ちました。
子ども3人同じように育てていても、三人三様だと実感しています。
感想・気づき
ゆっくりでいい
「正解のない時代に正解を求めている」、「みんながレーシングドライバーの運転スキルを求めている」
ほんとにそういう傾向はあると感じます。
本当はもっとゆっくりでいいのに。
親は、「人材育成」をしているわけではありませんよね。
学校や社会がそういう傾向にあるからこそ、親は逆にゆったりと構えておくという気持ちを忘れないようにしたほうがバランスがとれていいのかなと思います。

そんなことを考えていたら、
武田鉄矢氏のお母さま(武田イクさん)の著書の内容を思い出しましたのでご紹介します
今は時代がちがう。学校に行け、勉強しろ、成績上げろ、試験に通れ、ちたいな競争競争で子どもは大変じゃ。
もし子どもが学校へ行きよって学校がイヤになったらね。今ならもう学校へやらん。
学校へ行けば行くほど元気がなくなるようじゃったら休ませなしょうがないもんね。
昔は落第てさせよりましたね。あれもいいかもしれん。
ちょっと休憩して、もう一年やってみよかで、またやればいいんだから。
「なんばしよっとか」(武田イク著より引用)
こういう考えをどこかに持っておいたほうが、バランスが保てるのかなと思います。
実際に子育てされて、生き抜いてこられた方の言葉はしみます。
武田イクさんありがとうございます。
学校はダメでいい
おおた氏は最終章で「学校に理想を求めない」「学校はダメでいい」「学校のネガティブな部分に自分自身が染まらなければいいだけ」と述べられています。
いまの学校にはダメなところもいろいろありますけど、それはそれでいいんんじゃないですか。
だってどうせ、人間はダメダメだし、だからこそ愛おしいんだから。
「学校に染まるな!」(おおたとしまさ著より引用)
わたしも100点満点の完璧な人間ではありません。(最近は気楽に50点を目指そうとか考えているくらいです。)
人としても、親としてもまだまた人生の学びの途中です。
だから、学校にも100点満点を求めないということだと思います。

ちなみに、おおた氏は中学受験の本も多数出版されていますが、その中でおすすめの本は「勇者たちの中学受験」です
親子3組の実話をもとにした内容で、中受にもいろいろな体験があるんだなと驚きながら読みました
また、今回の内容に関しては、「やりすぎ教育」の記事も参考になるかと思います▽
また、書きます。