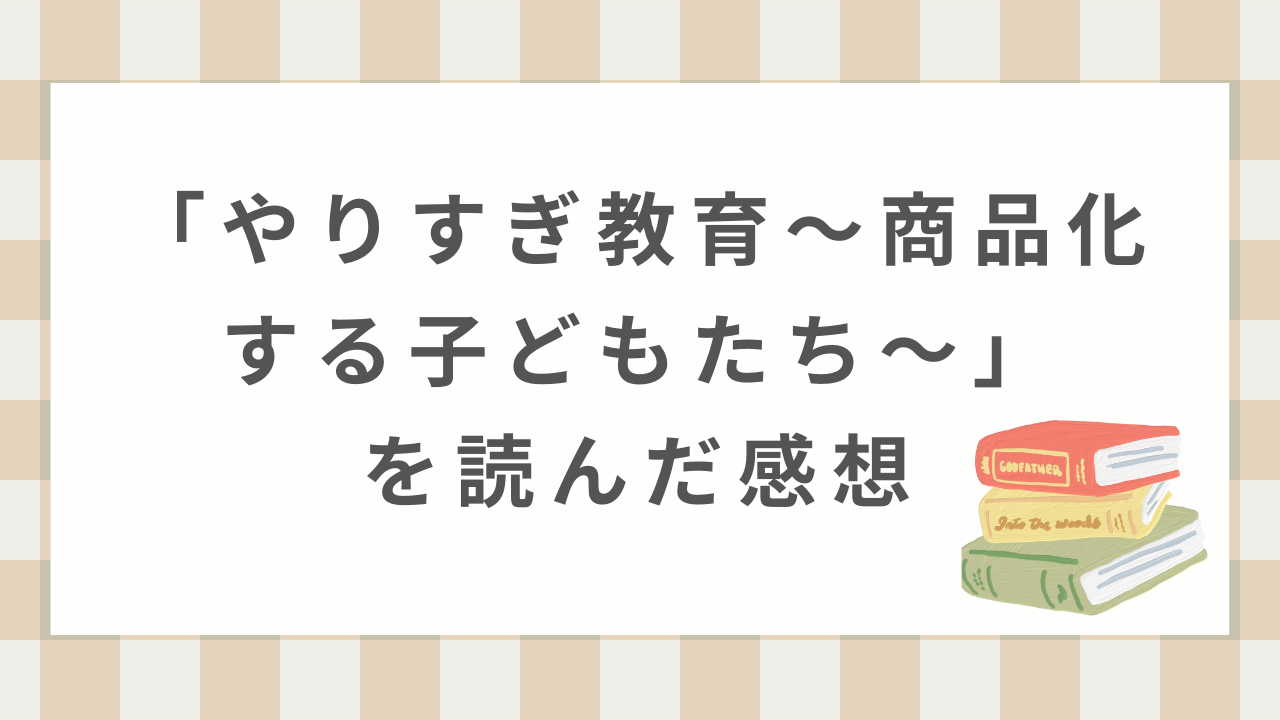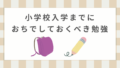こんにちは。さんははです。
今回は、「やりすぎ教育~商品化する子どもたち」という本を読んだ感想をお伝えします。
本の題名が衝撃的ですが、今の子育ての主流が、残念ながら本の題名通りのような気もするので、自分がそうならないために読んでみました。
少し学問的で資料や言い回しが難しい印象の本でしたが、内容としては「確かに・・・」と思う内容でしたので、内容ざっくりまとめてご紹介します。
本の内容
著者は武田信子さんという臨床心理士の方です。臨床心理学・教師教育学がご専門で、長年子どもの養育環境の改善に取り組んでこられたそうです。
題名の通り、「商品化」する子どもたちのことを危惧されていて、子育てがまるでブロイラーの養鶏のような状態になっていると表現されています。

そして、今の子どもたちをとりまく教育環境についてのさまざまな問題点を挙げておられる中で、日本の教育をとりまく現状をこのように名付けられていますので、引用します。↓
子どもたちが自分の生きる世界を理解して把握するために学びたいという、真の人としての成長発達のニーズでなはく、大人の将来への不安や欲望から強制的に学ばせられる状態のことを、私は「エデュケーショナル・マルトリートメント」と名付けました。これは親による教育虐待だけでなはく、社会全体の歪んだ教育観によってなされる、大人たちから子どもたちへの不適切な行為のことです。
「やりすぎ教育」(武田信子著) より
マルトリートメント(Child maltreatment)について調べましたが、この表現は、1980年代からアメリカで広まった表現で、日本語では「不適切な養育」「虐待」「さけるべき子育て」等という意味合いになるそうです。
武田さんは、日本の教育環境がこのような「不適切な教育環境」になっていると危惧されています。
例えば・・・
●親が将来への不安から成功できる大人に育てなければならないという思いが強くなっている点
●そのために、親や教育業界がすぐに点数や成果を結果として求める傾向が強くなっている点
●親以外の親族や地域の見守りが減り、親子ともども様々な価値観や人間関係に触れる機会が少なくなっている点
●子どもが自由に遊ぶことができる時間や場所が減っている点
●臨床心理学や精神医学によるアプローチが根本的な解決にはなってこなかった点
などを挙げておられます。
そして、これらの解決のためには、
学校教育のあり方や受験・評価のシステムや大人の持つ価値観の問い直しが必要で、個人を責めるのでなはく、社会全体で「やりすぎ教育」を予防していくべきだ考えられています。
感想・気づき
さんははの感想を書きます。
確かに武田さんのおっしゃっていることはもっともだと思いますし、実際に子育てをしている一人の母として、今の子どもたちが「やりすぎ教育」のようになってしまう確率は高くなっていると実感しています。
そして、それはその親だけの責任でも価値観でもなく、先の見えない社会状況や、格差社会の問題、学校教育の問題、受験の問題、等・・・社会の問題が複雑にからみあった結果であるので、社会全体で問い直しが必要だということも。。。

だけど、一人の母親として、社会全体の価値観の問い直しなんて難しいですよね。
この教育環境の中でも、健全に子育てをしていく道を見つけていくしかありません。
親としては、わたしは、自分の子育てを問い直していくことしかできません。
「一隅を照らす」そんな気持ちでいます。。。
避けるべきは、武田さんがおっしゃっているように
教育熱心な親は、非認知能力が大事だと言われればキャンプに連れていき、感性が必要だと言われれば、五感を育てることを謳う(うたう)教室に通わせるというふうで、何としてでも子どもを高得点の子どもにしたいと思っています。
「やりすぎ教育」(武田信子著)より
このような親の考え方をやめることだと感じます。
親として、こんなふうに世の中のはやりに影響されるのではなく、自分の子ども一人ひとりに合った教育環境を見つけていくことが一番大切なのではないかな・・・と思います。
世の中にはたくさんの道がありますが、必ずしも目指した道に進めるとも限りません。
また、思い通りにならないことの方が多いでしょう。
今の世の中は一度レールから外れてしまうとなかなか戻りづらい社会構造になってしまっていると感じます。
厳しい世の中を生きていかなくてはならない子どもたち。
だけど、たくましく生き抜いていってほしい。
だけどやりすぎてもいけない、ほうっておいてもいけない。。。
「中庸(ちゅうよう)」(かたよることなく、常に変わらないこと。過不足がなく調和がとれていること。)が大事なんだと思います。
世の中に出たら大変だからこそ、
子ども自身がどのような道に進んでいきたいか、どのような道が向いているのか、どのような道が可能なのか、そのためにどうしたらよいのか、
子どもがゆっくり考えられる明るさと静けさを与えてあげて、親として励まし待てる心の余裕が大切なんだと思います。
こんなことを考えていたら、以前に読んだ本(別の著者ですが)に書いてあった内容を思い出したので、最後に紹介して終わりたいと思います。
目先にこだわるな
世の中は十分広く、やるべきこともたくさんあります。目の色を変えて集まるところだけが天下の道ではなく、あまりにも人の少ない道もあるのです。細くとも、月を眺めながら、自信をもって悠々と行ける道もあります。
「さあ、がんばろう」(平澤興著)より
こんなふうに考えられる心の余裕を忘れないようにしたいな・・・と思います。
また、書きます。